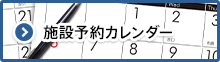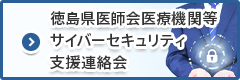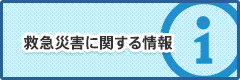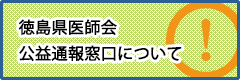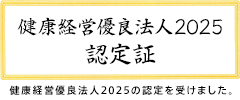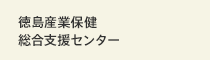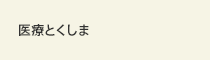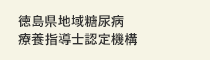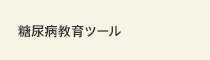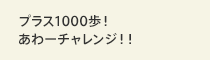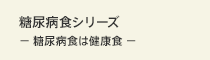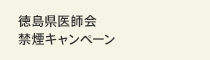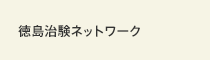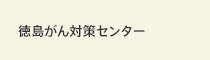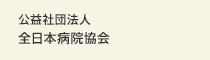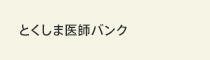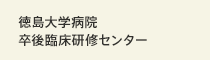注意欠陥多動性障害の頻度は3~7%とされます。多くは学童期に診断され、成長するにしたがって頻度は減少します。しかし学童期に注意欠陥多動性障害と診断された人でも、思春期には70%、成人期にも30~50%が症状を持ち続けて、日常生活に何らかの支障があると推定されています。
多動を主症状とする注意欠陥多動性障害には多動と衝動性を特徴とする多動性・衝動性優勢型と不注意を特徴とする不注意優勢型、およびその混合型があります。もっとも多いのは混合型で50~60%を占めます。不注意優勢型は25~30%、多動性・衝動性優勢型は15~20%であるとされます。
男女比は8:1と圧倒的に男子に多いとされます。これは幼児期後半から学童期には多動性や衝動性を示す男子が目立ち、診断されやすいためと考えられています。不注意優勢型の女子は診断されずに放置されている場合があります。女性は成人してから、片付けられないとか捨てられないなどの症状が問題になって、本症と診断されることがあります。したがって実際の男女比は2.5~5:1くらいと言われます。
本症の症状は年齢によって変わります。
学童期では学校生活の中で問題になる症状は、着席できない、列を離れる、おしゃべりする、手を挙げないで答えてしまう、ルールに従わない、友達にちょっかいを出す、短気である、仲間に入れてもらえない、言いつけを守らない、宿題を終わりまでやらない、日課を忘れる、身の回りのことをしないことなどが上げられます。
思春期になると、学校生活で忘れ物、課題を最後までしない、積み重ねの必要な学習をしないなどに加えて、不安や抑うつ、非行などの問題行動が出てくることがあります。
さらに成人期には、仕事を頻繁に変える、長く単調な仕事に注意を集中し続けるができない、金銭・旅行・仕事その他の企画に衝動的な判断をする、自動車事故が多いことなどが出てきます。
県民の皆さまへ
注意欠陥多動性障害 -2-
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
2008年9月17日掲載