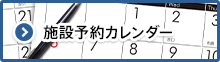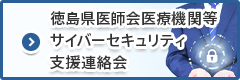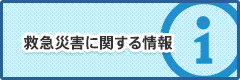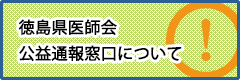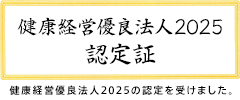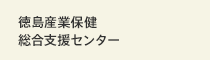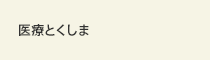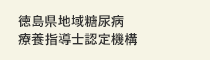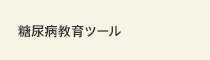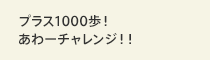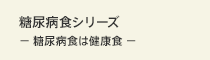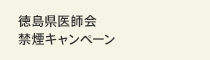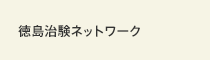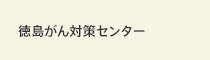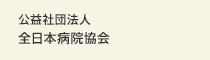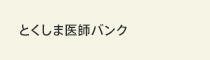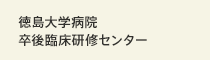- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
体温は体温調節中枢によって一定に保たれていますが、子どもは体温の変動幅が大きく不安定な場合があります。また抵抗力が弱く感染症にかかる機会が多いために発熱する機会が多くなります。
一般に発熱の原因は感染症、膠原(こうげん)病、悪性新生物の3つが代表とされますが、子どもの発熱の原因で圧倒的に多いのは感染症によるものです。したがって子どもの発熱を見た場合にまず感染症を考えます。
この時にもっとも注意すべき条件は子どもの月齢(年齢)です。
新生児の発熱は敗血症や髄膜炎など重症の細菌感染を考え、新生児の専門施設で検査、治療することが原則です。
3カ月未満の乳児の発熱は新生児に準じて注意すべき必要があります。敗血症、髄膜炎、尿路感染症、腸管感染症、骨髄炎など重症の細菌感染症を考慮して厳重に取り扱います。これらの重症感染症に対する検査ができ、すみやかに治療ができる施設に入院し、経過観察することが求められます。
生後3カ月を過ぎて2歳くらいまではもっとも感染症にかかりやすくなり、一般の小児科医を受診する機会が多くなります。
幼児期後半から学童期になるとだんだん発熱する機会は減少しますが、その代わり集団生活に入ることから、流行性疾患にかかることが多くなります。ただ、この時期には体力や抵抗力が増してきますから、感染症が急に重症化することも少なくなります。発熱の原因を見極めて対応することができるようになります。
発熱は多くの場合、感染症によって増加した体内の発熱物質が体温調節中枢を刺激して設定温度を上昇させるものです。これは免疫反応のひとつです。したがって発熱したからといってすぐに解熱剤の投与を考える必要はありません。解熱剤はあくまで対症療法であり、感染症の根本治療ではないのです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
子どもの発熱は小児科受診原因の第1位です。発熱は子どもにとってもその家族にとっても大変な重要な症状です。また私たち小児科医にとっても、発熱の原因を特定して適切な治療を行うことが求められ、小児科診療の上でも大切な徴候のひとつです。
子どもの体温は成人に比べて高めであるとされます。これは乳幼児では成長のために新陳代謝が活発で熱産生量が多いためです。
体温は中枢神経系で調節されて常にほぼ一定の範囲に保たれています。これが平熱です。
平熱には個人差があります。普段から熱を測って子どもの平熱を知っておくことが大切です。ただし体温は測定場所や測定時間によって変動します。乳幼児では脇の下で測定して37.2~37.3℃は平熱とされます。口腔内や直腸内で測定した体温は脇の下で測定したものより高めに出ます。
また体温には日内変動が見られますから、夜明け前の体温は1日の中でもっとも低く、夕方の体温はもっとも高くなります。
体温を調節する中枢は脳内の視床下部にあります。視床下部が設定した体温が平熱です。体温は熱産生量と熱放散量のバランスで決定されます。毎日同じような生活をしていれば熱産生量はほぼ一定です。したがって熱放散量を調節することによって体温は一定に保たれます。
体温は血管の拡張・収縮による体表面からの熱放散、血流や呼吸による調節、発汗による蒸散など自律神経を介して調節されます。体温が上がりすぎれば抹消の血管は拡張し、血流や呼吸数が増加し、発汗による蒸散が増加することで熱の放散量が増加します。体温が下がれば抹消血管は収縮し、血流や呼吸は遅くなり、発汗による蒸散も減少して熱放散量が減少し体温を維持するように働きます。
からだの小さな子どもほど平熱は高く、1日の中での変動幅も大きくなります。また乳幼児の体温は衣服や環境の温度、睡眠、食事、運動などの影響を受けやすいものですから、測定条件を一定にして測定することが大切です。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
インフルエンザの治療薬タミフルによる行動異常が問題になっています。タミフル服用後、走り回ったり窓から飛び降りたりして生命を失う場合があったためです。
インフルエンザの治療薬として抗ウイルス剤が出現して、インフルエンザの治療は飛躍的に発展しました。しかし抗ウイルス剤の使用にともなう副作用や耐性ウイルスの出現などさまざまな問題も明らかになってきました。また症状の比較的軽い場合にも抗ウイルス剤が使用されている場合もあります。
インフルエンザにはかかる前に予防することが大切です。予防接種の効果は100%ではありませんが、血液中の抗体価が高ければ重症化することは防ぐことができます。
インフルエンザが発生したときにはできるだけ患者を隔離してウイルスを閉じ込めることが大切です。とくに学校や保育園など集団生活の場所では完全に治るまで休むことが求められます。
インフルエンザウイルスは患者の鼻みずや痰(たん)の中に含まれ、咳やくしゃみで周囲に伝播されます。室内の温度や湿度が高ければ問題はありませんが、寒くて乾燥した環境では長時間感染力を保つとされます。基本的には飛沫(ひまつ)感染ですが、接触や空気感染もあると考えたほうがいいでしょう。
インフルエンザを予防するためにはマスクが役に立ちます。ウイルスはマスクを通過しますが、ウイルスを含む患者さんの鼻みずや痰を吸い込まないようにすることができます。またマスクは口や鼻の周囲の保温、保湿にも役に立ちます。鼻がつまって口で呼吸をしている場合、寝ているときにもマスクをするといいでしょう。
昔からよく言われるように暖かくして十分な栄養と睡眠をとることが大切です。外出時にはマスクをすること、帰ったらうがいや手洗いをしっかりすることでインフルエンザウイルスの侵入を減らすことが大切です。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
インフルエンザは高熱をともなう冬のかぜの代表です。体力や抵抗力のない子どもにとって大変つらい病気です。
しかし最近登場した抗ウイルス剤はインフルエンザの治療を大きく変化させました。発病後48時間以内に診断をつけて抗ウイルス剤を投与すると速やかに解熱し、肺炎などの合併症も少なくなることが知られます。
ところが抗ウイルス剤の投与を受けた人の中から異常行動を示す例が報告されるようになったのです。走り出すとか、窓から飛び降りることによって、生命を失う人が出てきました。
その結果を重視した厚生労働省は10歳代のインフルエンザに抗ウイルス剤タミフルの投与を原則禁止としたのです。
インフルエンザはもともと高熱をともなう疾患ですから熱性けいれんや熱せん妄と呼ばれる異常行動をともなうことが知られています。異常行動には突然走り出すとか、飛び降りるなどの予測できない行動で誰かが制止しなければ生命に危険が及ぶものから、会話が突然通じなくなる、おびえる、無いはずのものが見える、無意味な動作をくり返すなど、その行動自体では直ちに生命に危険は及ばないものの普段は見られない異常行動まであります。
異常行動は神経疾患の存在や薬剤の神経系への影響を疑わせるもので、とくに意識障害をともなう場合やけいれん重積症をともなう場合にはインフルエンザ脳症との区別をすることが大切です。
10歳代の患者さんにタミフルの使用ができなくなった今シーズンのインフルエンザの治療には多くの医師が困惑しています。今後の治療としては、他の抗ウイルス剤や漢方薬などの使用が考えられます。
しかしインフルエンザそのものに異常行動が見られるので、他の薬剤を多く使用すればタミフルと同様の異常行動が見られることが予想されます。
インフルエンザにかかった場合には治療の有無にかかわらず2日間くらいは子どもから目を離さないようにすることが大切です。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
毎年冬になるとインフルエンザが話題になります。今シーズンのインフルエンザは昨年11月ごろから東京をはじめ各地で流行し、例年より1ヶ月ほど早い流行が伝えられました。
インフルエンザは高熱をともなう伝染力の強いウイルス疾患です。せきや鼻水などの一般のかぜ症状のほかに下痢や嘔吐(おうと)などの消化器症状も見られます。高熱のために熱性けいれんを起こすこともあります。肺炎などの呼吸器系の合併症も多く、体力や抵抗力の弱い乳幼児にとっては大変な疾患です。
インフルエンザは検査法の進歩や抗ウイルス剤の登場などによって10年前には考えられなかったほど、診断や治療に大きな変化が見られるようになりました。
以前、インフルエンザの診断にはウイルス分離や抗体価の測定など時間のかかる検査しかありませんでした。ウイルス分離は特別な施設でしか検査できませんし、検査に日時がかかります。また抗体検査は感染してから上昇するまでに日時がかかり、結果がわかるのはインフルエンザが治った後です。したがってこれらの検査は実際のインフルエンザ治療には利用できませんでした。
しかし最近は迅速診断キットが簡単に使用できるようになりました。鼻腔(びくう)粘膜や鼻汁から採取した検体で検査すると10分くらいでインフルエンザかどうかの結果とともに、A型かB型かの区別もわかるようになりました。
検査の精度は80~90%で完全ではありません。また検体採取の時期によってインフルエンザであっても結果が陰性に出ることがあります。しかし流行状況や症状、診察所見に加えて検査結果を参考にすればかなり正確な診断をつけることが出来ます。
正確なインフルエンザの診断ができれば効果的な治療ができるために、抗菌剤などの不必要な薬剤の使用を減らすことも出来ます。確実な診断が治療の第一歩です。